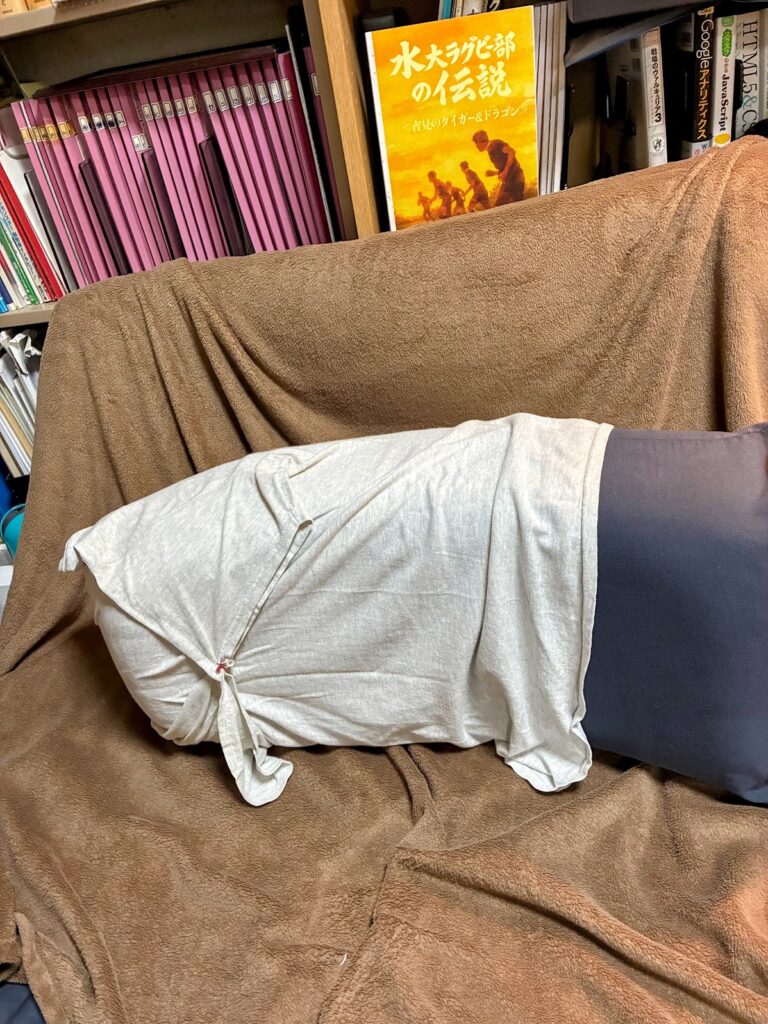18年前に魚河岸小僧を辞めたとき、
水産の道から外れるのは本意ではありませんでした。
森下で乗り換えれば30分で来られる距離なのに、
今日まで一度も築地へ足を向けることはありませんでした。
ところが今年に入り、20代の築地の思い出を書き、
Kindle本として出版したことで、
あの頃の記憶が心の底から浮き上がってきました。
平日に休める日もできたので、
今日は一眼レフを持って昼下がりの築地をぶらぶら歩くことにしました。
若い頃、私は勝どき2丁目の交差点角のワンルームに住んでいました。
当時は大江戸線がなく、築地駅まで歩くか、
東京駅・門前仲町方面へ都バスで通っていました。
今日は大江戸線の勝どき駅で下車し、
晴海通りを北上して勝鬨橋へ向かうつもりでした。
ところが地上に出ると、そこは予想外の高層ビルの谷間。
 勝鬨橋が全然見えません
勝鬨橋が全然見えません
トイレを借りようと公園に寄り、戻って歩き出したら、
なぜか勝鬨橋ではなく築地大橋の袂に出てしまいました。
「こっちから勝鬨橋を見た方がええよ」
そんな声が、お空のアカサカ君から聞こえた気がしました。
築地大橋は、私が魚河岸を去る頃に工事していた橋です。
 築地大橋から見た勝鬨橋
築地大橋から見た勝鬨橋
今日、初めてその橋を渡りました。
そこから市場跡地をなぞるように歩き、
正門ゲートを越えて波除さんを目指しました。
途中の場外は、月曜の昼下がりとは思えないほど観光客で溢れていました。
 場外の並びは昔のままでした
場外の並びは昔のままでした
波除さんは、市場が消えてもそこだけは変わらず残っていました。
海幸橋も、宝くじ売り場や七味屋さんがあったあの場所がそのまま残っていました。
そして、私が働いていた雑居ビル。
周囲は建て替えられて大きなビルになっていましたが、
そのビルだけはまだ現存していました。
地下の食堂の看板も当時のまま。
 魚河岸小僧時代の基地
魚河岸小僧時代の基地
階段を降りると、地上の摩天楼とは別世界。
地下だけは、あの頃の空気がそのまま残っていました。
席に座り、自然と口から出た注文は「B定」。
20代の頃、なぜかいつもこればかり食べていました。
迷わず、外さず、腹にしっかり入る。
仕事のリズムにぴったり合う“身体が覚えた定食”でした。
14時頃でしたが、6〜7割の席が埋まっていました。
皿が運ばれてきた瞬間、
「電話してて昼を食べ損ねて、6階から古いエレベーターで降りてきた自分」が
また現れるんじゃないかと思うほどでした。
 B定食も昔のまま
B定食も昔のまま
市場跡地を一周したことで、今日は十分満足しました。
帰りは勝鬨橋を渡りました。
上流側の岸辺をどうしても見たかったのですが、
掛け替え工事で囲われていて見られませんでした。
 右側のアーチの先が囲われていて、思い出の岸辺に行けませんでした
右側のアーチの先が囲われていて、思い出の岸辺に行けませんでした
それだけは残念でしたが、
心の深いところにある“大岩”を、今日は確かに見ることができました。