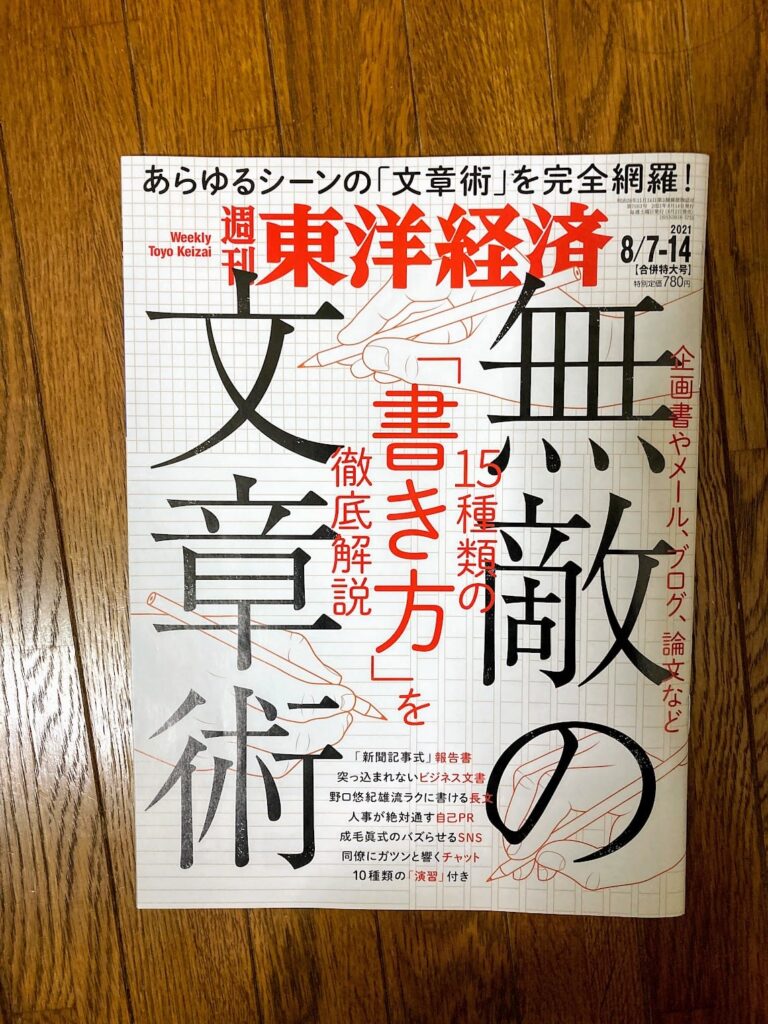仕事の合間を縫い、海幸橋を渡って場内へ繰り出す時間は、
築地で働く者だけに許された小さなご褒美だった。
橋の上を吹き抜ける潮風の向こうに、
湯気と匂いが渦巻く“食の聖地”が広がっている。
「豊ちゃん」の乗っけは、
皿の上に惜しげもなく重ねられた揚げ物とご飯の重さが、
朝の労働で空っぽになった身体にずしりと染み込んだ。
「中栄」のインドカレーは、
スパイスの香りがセリ場の冷気を一瞬で吹き飛ばし、
汗が額をつたうほどの熱をくれた。
「ふぢの」のラーメンは、
市場の喧騒をそのままスープに溶かし込んだような味で、
食べ終わる頃には指先まで温まっていた。
そして「吉野家」の牛丼は、
築地で働く者にとって“帰る場所”のような存在だった。
時には、大和寿司へ電話を入れる。
「今から行くよ」と告げると、
大将は裏口を少しだけ開けて待っていてくれた。
行列客の視線を背中に感じながら、
そっと忍び込む。
カウンターの奥で、大将が“ちびけた出刃”を手に、
脂の乗った身を静かに切り出してくれる。
その一切れを口に運ぶ瞬間、
築地で働く者だけが知る“粋”が舌の上に広がった。
もちろん、後で事務所に届く請求書は高額だった。
それでも、
あの味、あの空気、あの背徳感は、
築地で働く者の誇りの一部だった。
市場の冷気と鉄の匂いの中で働くからこそ、
この一杯、この一切れが、
何よりも尊く感じられたのだ。